

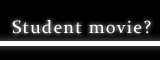


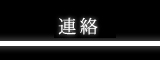
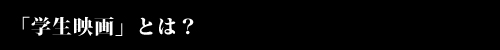
日本にも映画・映像を教えている大学や専門学校は数多く存在します。
更には、数多くの大学に映像・映画のサークルや部活が存在し、
そのそれぞれが毎年新たな若さあふれる作品を発表しています。
学生映画のなかにも小規模な数分の作品から、大規模な長編作品まで存在しますし、
制作される理由も、授業課題などから酒の勢いまで多数あって、
なかには商業作品ではありえないようなユニークなアイデアの作品も存在します。
学生映画を専門にした映画祭も国内に存在しています。
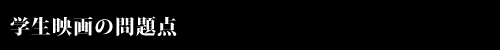
しかし、圧倒的にたくさんの数の作品が制作されていながら、何故か映画祭などで入賞するのは
社会人の制作した作品が多い現状があります。
また事実、一般の人に「学生映画」と言うと、訴求力に欠けると言わざるを得ません。その理由を考えると、経験不足や技術力不足、さらには資金力の無さといった理由以上に、
学生の制作する映画には、制作者側にとって“遊び”、あるいは“内輪受け”の要素が強い、
という理由があります。本来、映画は見る人のために存在しているはずです。
しかし学生映画においては、その存在意義が、見る人への娯楽から、
作る人への娯楽に変化してしまう逆転現象が存在します。
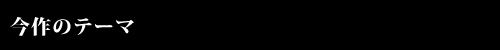
今作は、そういった「学生が映画を撮る行為」そのものに対して切り込みます。
一人の学生である主人公が映画を撮ろうとする中で、上に書いたような、
「どうせ学生映画なんて自分たち身内しか見ないんだから、それで良い」
という考えと触れていきます。しかし、映画とはお客さんがエンドロールまで見てくれて初めて
存在意義が発生するのではないか、と主人公は考えます。学生映画とは、自分たちのための物で良いのか?
ある意味答えのないテーマですが、今回はより深くその学生の“遊び”に
切り込むことを目指します。
そして、その映画自体もまた学生映画であることによって、
よりそのテーマへのアプローチを鋭角化します。